この記事は、ゼミ生の個人的な意見や年度によって異なる情報を含む可能性があります(それ以外は2025年度募集要項より引用)。最新情報はゼミ募集要項をご確認いただくか教授・教務入試班にお問合せ下さい。
ページコンテンツ
01.受け入れ学科・コース
学部生:ロシア学科の語学文学・多文化共生・リベラルコース、その他学科の多文化共生・リベラルアーツコース
二部生:受け入れ無し
02.研究内容
児童文学を研究対象とし、外国の文学を日本に紹介したり日本の文学を海外に紹介したりする際に生じるあらゆる問題を探求。授業では子供の本の翻訳研究の様々な文献の講読および翻訳分析と議論を行う。
教授の研究分野はこちらから!↓↓
ロシア学科教員 E.Baibikova准教授
03.授業について
授業の進め方
前期:学術論文の書き方に関する理解を深めながら、講読やレジュメ作成・プレゼンなどを行う。
後期:自分の研究計画を立て、発表を行う。
3年時から卒業までに原則として以下の科目単位の習得が必要:
長沼美香子先生担当「翻訳理論」
英語の学術論文を読む (TOEIC785) 能力が望ましい
なお、ロシア学科の学生は、ロシア語能力B1レベルに相当する能力を有する (B2レベルのロシア語能力があること
が望ましい)
課題(2022年度までの情報を含む)
3年生前期のうちだけ先生に与えられたテキストを読解するなどの課題がある。
後期からは自分の活動に集中するようになると思うので自然と課題はなくなる。
その代わり、卒論のための研究などを行うので自分の研究に関するプレゼンの番が回ってくる。
04.評価
出席や参加態度30%
発表30%
翻訳・レポート・課題40%
05.いいところ!(昨年度までのゼミ生の声)
研究面
児童文学というジャンルにしても、非常に様々な領域を扱うことが出来る。
小説(テキスト)だけでなく、絵本、昔話や民話、マンガなどなど媒体を挙げてみても様々。
なので、自分が興味のある分野で研究をすることが出来るのが魅力!
研究以外
先生が優しいというのは本当に強調したいところ。
かなり学生に寄り添ってくださる先生✨🙂
06.ゼミの推しポイント!(昨年度までのゼミ生の声)
ゼミ生のほとんどが女性ということもあってか、明るくて優しい雰囲気のゼミです!
07.卒論
必須 (ロシア語または英語)
研究内容は人によるが、「児童文学の翻訳ゼミ」と銘打ってはいるもののその研究内容は多岐にわたっており、それぞれがそれぞれ興味のあることをしている。
昨年度までの情報によると、例外的に翻訳レポート(翻訳された文章に自分の解釈をつけるもの)でも卒論と認められるようだが、今のところ翻訳レポートを書いている人は見たことがないそう。
テーマ例:「新旧翻訳比較」「翻訳者の人生」
08.選考について
メールでアポイントメントを取った後、研究室にて面談。
イスパニア学科3回。スペイン語に大苦戦中。音楽とお笑いが好き。

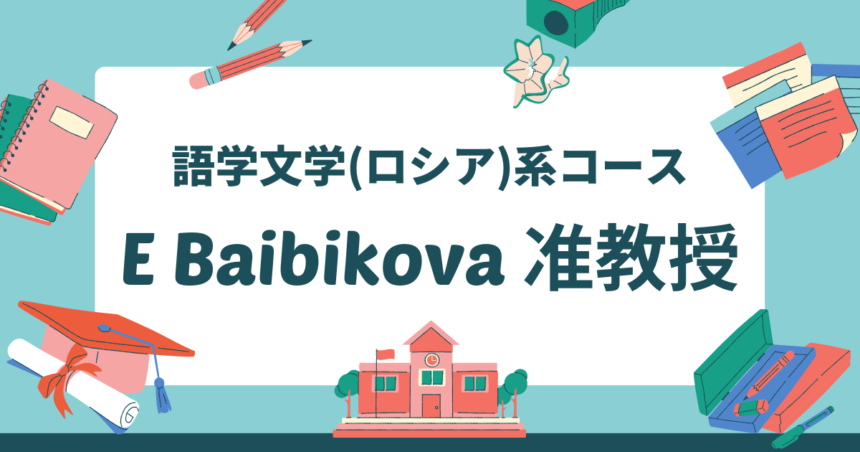
.png)
-1.png)

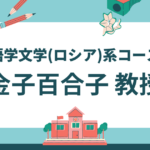
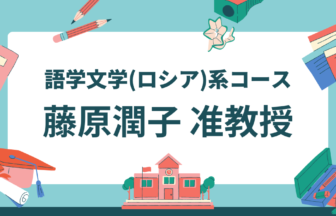
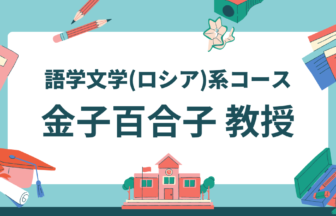
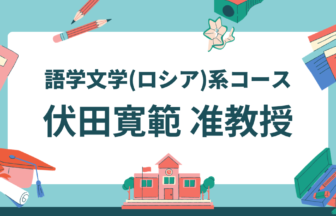
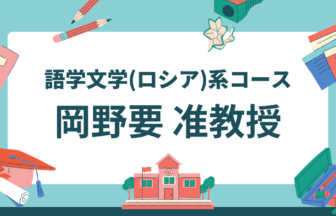
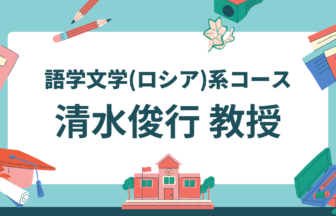
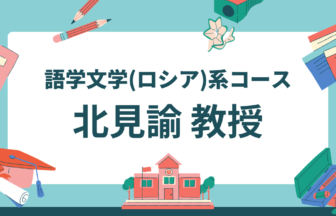
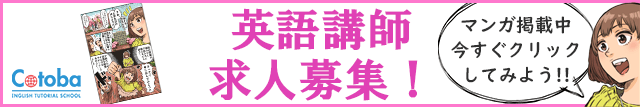
この記事へのコメントはありません。